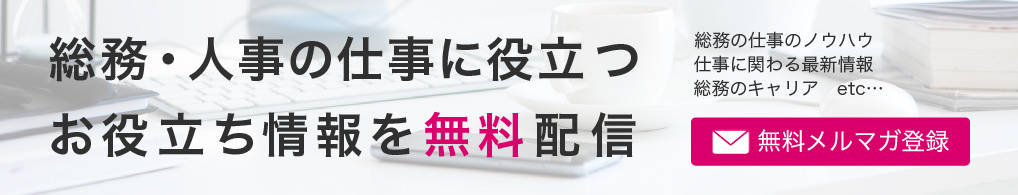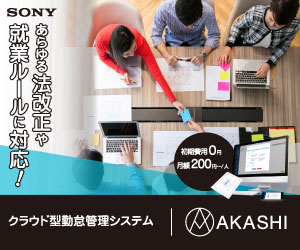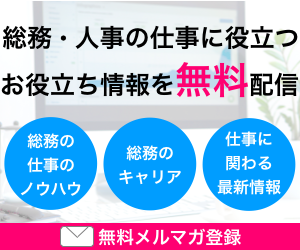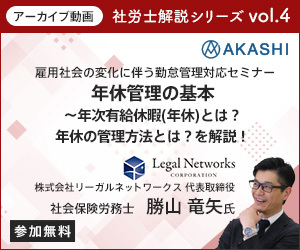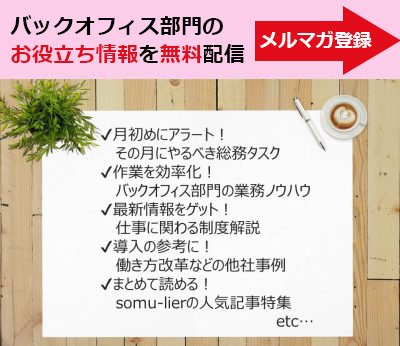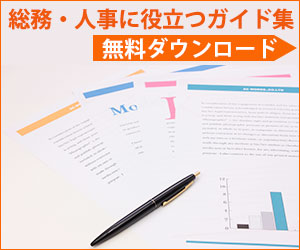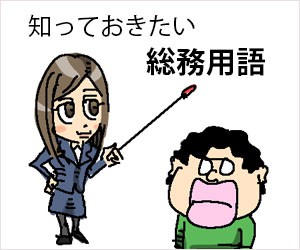改正薬機法が施行され、虚偽・誇大広告を行う企業に対する課徴金制度が実施されました。医薬品や化粧品を販売するメーカーのみならず、広告代理店などにも影響がある法改正なので、規制内容を確認しておきましょう。今回は薬機法の規制内容や改正された点と罰則、違反を防ぐポイントについて解説していきます。
目次
薬機法について正しく学ぼう
薬機法とは
薬機法は、2014年(平成26年)11月に従来の薬事法が改正され、名称変更とともに施行された法律です。正式名称を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。この法律では、医薬品などについて、製造・販売・安全対策までを規制し、その適正化をはかることを目的としています。
規制対象
薬機法の規制対象は以下の通りです。
- 医薬品
- 医療機器
- 医薬部外品
- 化粧品
- 再生医療等製品
薬機法の規制対象について注意するべきは、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品なども含まれる点です。
ちなみに、健康食品やサプリメントは、薬機法上の定義はなく、一般食品(国が認めた特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品は除く)と同じ扱いです。そのため、医療品のような効果を訴求すると、無承認無許可医薬品として薬機法に抵触するため、注意が必要です。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品についても、効果や機能性について消費者庁長官から認められた内容以上の表示はできないとされています。
規制内容
薬機法で規制される内容は、大きく分けて下記の2点です。
- 各段階規制
医薬品・医療機器等の開発について、「開発・治験」「承認審査」「製造」「販売規制」「市販後安全対策」「監督指導」「副作用被害の救済」の各過程で必要な規制や承認審査のルールを設けています。 - 広告規制
医薬品・医療機器等の広告を行ううえで、虚偽・誇大広告の禁止、特定疾病用医薬品等の広告制限、未承認医薬品等の広告の禁止などを定めています。
なお、虚偽・誇大広告に対する禁止の対象は、広告主(メーカー)に限らず、広告代理店、広告を掲載するメディアはもちろん、インフルエンサーなどの個人も対象になります。
・関連記事
・領収書の提出が不要に? 医療費控除について解説!
・払いすぎた税金が戻ってくる? 還付申告の手続を解説
・その費用、損金になりますか? 広告宣伝費と交際費の違いとは
企業が気をつけるポイント
課徴金制度
課徴金制度は、薬機法第66条「虚偽・誇大広告の禁止」の条文に違反する行為が対象になります。
課徴金は、原則として違反していた期間における対象商品の売上額の4.5%が徴収されます。ただし、課徴金が225万円(対象品目の売上げが5000万円)未満の場合は対象外です。このとき、同一の事案に対し、景品表示法の課徴金(売上額の3%)がある場合は、この額を控除した売上額に対して課されます。また、課徴金対象行為に該当する事実を、事案発覚前に違反者が自主的に報告したときは50%が減額されます。
薬局開設者などのガバナンス強化
相次ぐ薬機法違反に対する防止措置として、今回の薬機法改正に伴い、法令順守に関する体制の整備を行い、薬局開設者のガバナンス(企業統治)強化が義務付けられています。大まかな内容は下記の通りです。
- 遵守すべき規範を、社内規定において明確に定め、周知すること
- 薬事に関する業務に責任を有する役員を位置づけること
- 責任役員の権限や分掌する業務・組織の範囲を明確に定めて周知すること
- 役職員の意思決定や業務遂行の業務記録を作成の上、管理及び保存する体制をとること
- 管理者は必要な能力と経験を有する者を選任し、権限を明確化すること
- 管理者による意見申述義務と、薬局開設者等の意見尊重や措置義務を定めること
上記のような対策が不十分である場合は、改善命令の対象となります。
薬機法に違反した際の罰則
薬機法に違反した場合、2年以下の懲役、200万円以下の罰金、または両方が課されます。また、2021年8月からは薬機法が改正され、売上に対する4.5%の課徴金も課されるようになりました。薬機法違反の例としては、医薬品の製造販売業や医薬品の販売業などに違反し、医薬品等を無許可で製造・販売することが挙げられます。この場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方が科せられるおそれがあります。
薬機法違反には、行政処分に加えて刑事罰を受ける可能性もあります。違反した者(代表者など)は逮捕され、刑罰には罰則と罰金があり、最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が課せられることもあります。薬機法に違反した場合は、違反者や事業者に対して行政指導が入るのが一般的です。しかし、その内容が悪質だと判断された場合には、刑事罰として懲役刑、または罰金が課される場合もあります。
薬機法の違反を防ぐためのポイント
薬機法の勉強会を開催する
薬機法に違反しないためには、社内勉強会の開催が効果的です。勉強会では、「医薬品等適正広告基準」などの、厚生労働省が定めているガイドラインの確認をしましょう。普段から薬機法の内容に触れる機会の多い部署のほかは、これらの認識が不十分になる可能性があるため、全社的に行うことが重要です。広告のキャッチフレーズなどは、効能の強調や、優良誤認を招く表記をしてしまいがちであることに加え、広告・宣伝の業務に関しては、外部委託の機会も多いため、いち担当者に至るまでしっかりと認識する必要があります。
社内で広告ガイドラインを作成する
薬機法による広告表現への規制は、細部に至るまで詳細に定められており、法律違反にならないためには細心の注意が必要です。そのため、自社の商品が訴求可能な効能範囲を把握し、その範囲で使用できる表現などをまとめた、社内広告ガイドラインを作成すると良いでしょう。このとき、不適切な表現と適切な表現の対照表を載せるなど、従業員にわかりやすい内容にすることが大切です。
・関連記事
・【シリーズ】社内広報のススメ1:「社内広報」でイキイキした職場をつくろう
・【シリーズ】社内広報のススメ2:「社内広報」はじめの一歩
・【シリーズ】社内広報のススメ3:読者に効果的に届けるメッセージのつくり方
・源泉徴収が必要な所得の範囲とは?―原稿料やデザイン料も、源泉徴収が必要です!
2022年改正のポイント
2022年改正による変更点から2点を紹介します。
緊急時の薬事承認
緊急時の薬事承認制度とは、緊急時に迅速な薬事承認を行うための制度です。通常の医薬品の承認審査とは異なり、臨床試験の途中でも有効性が推定されれば、条件や期限の下で承認を取得できます。
緊急時には、感染症のアウトブレイク発生や原子力事故、放射能汚染、バイオテロなどが想定されています。
緊急承認の要件は、「国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品等であり、ほかに代替手段が存在しないこと」と定められています。
電子処方箋の仕組み創設
電子処方箋は、処方箋を紙ではなくデジタルデータで運用する仕組みです。患者の同意を得た上で、全国の医療機関や薬局における過去3年間の薬剤情報や、直近の処方・調剤結果を参照できるようになります。
電子処方箋の仕組みの創設には、次のような内容が含まれています。
- 医師等が電子処方箋を交付できるようにする
- 電子処方箋の記録や管理業務を社会保険診療報酬支払基金等の業務に加える
- 管理業務にかかる費用負担や厚生労働省の監督規定を整備する
電子処方箋に対応している医療機関や薬局は、厚生労働省のホームページで確認できます。
まとめ
薬機法改正には、ネット広告を利用する事業者が増えたことにより、虚偽・誇大広告などの問題が深刻化していることが背景にあります。直近では、新型コロナウイルス感染症が流行するなか、未知のウイルスを恐れる消費者心理につけこむような、不確実な広告表現が問題視されています。そうでなくても、自社開発製品の効能をアピールしたい気持ちが、つい誇大広告表現となり、薬機法に違反してしまう事例も後を絶ちません。薬機法改正を機に、医療品などの開発会社をはじめ、情報発信や広告に携わる人も、薬機法の内容をしっかりと確認しましょう。