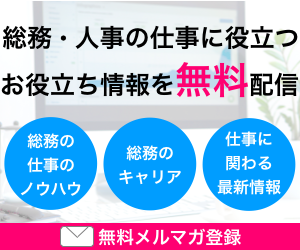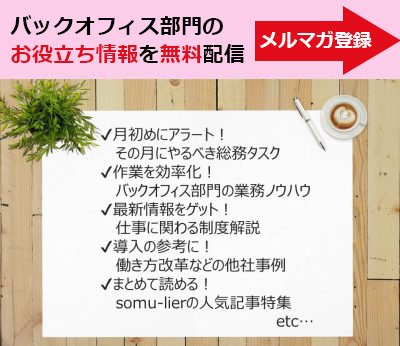多くの企業では、従業員の採用後3ヶ月程度の試用期間を設けています。試用期間中は通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められますが、試用期間の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合でしか解雇することはできません。
また、試用期間中であっても14日を超えて勤務した場合は解雇予告が必要となるほか、長期の試用期間は無効となるなどの制限があります。
今回は、試用期間の法的性質や、試用期間の運用にあたっての注意点について解説します。
目次
試用期間とは
試用期間とは、採用後に実際の勤務を通して従業員の適性などを評価し、本採用するか否かを判断するために企業が設ける期間のことをいいます。企業の多くは試用期間を設けており、その期間は一般的に「3ヶ月」とする例が多くなっています。
試用期間中の労動契約は、「解約権留保付労働契約」だと解されます。これは、契約締結と同時に雇用の効力が確定するものの、企業は契約の解約権を留保しており、試用期間中に当該従業員が不適格であると認めた場合は、それだけの理由で留保した解約権を行使し、契約を解約しうるという契約です。
判例では、このような解約権の留保は合理性があり、留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められるとされています。
関連記事:
・雇用のルールを完全マスター!労働関連制度まとめ<前編>
・雇用のルールを完全マスター!労働関連制度まとめ<後編>
試用期間中の解雇について
上記のとおり、試用期間中は通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められます。ただし、判例では、試用期間中の労働者が他の企業への就職機会を放棄していること等を踏まえ、留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨や目的に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められるような場合にのみ許されるとされています。
すなわち、採用決定後における調査や試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合で、解約権を行使することが客観的にも相当であると認められる場合にのみ解雇が認められます。
不当解雇にならない解雇事由
試用期間中の解雇が認められるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 勤務態度が極めて悪い場合
社内外で何度もトラブルを起こしていたり、上司の指示に従わなかったりした場合のように勤務態度が極めて悪いと判断されると、解雇が認められる可能性が高いです。しかし、勤務態度の悪さだけでは解雇事由にならず、指導や注意を繰り返しても改善が見られない場合に限られます。 - 正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返す場合
正当な理由なく遅刻や欠勤を繰り返す場合、まずは指導を行い、改善に務める必要があります。指導を繰り返しても改善の兆候が見られない場合、解雇が認められる可能性が高いと言えます。 - 本人の履歴に重大な虚偽の事実があったことが発覚した場合
応募の際の履歴書や職務経歴書の、学歴や職歴、犯罪歴、保有資格などに重大な詐称があった場合、解雇が認められる場合もあります。労使間の信頼関係を壊すことや、社内秩序を乱すことが争点となり、「詐称前の経歴なら雇用しなかった」となるほどの規模の詐称であれば、解雇事由と認められる可能性が高いでしょう。
試用期間中の解雇の手続き
試用期間中に解雇を行う場合に必要な手続きは、試用開始から解雇までの日数によって異なります。
試用開始から14日を過ぎて解雇する場合
試用期間中であっても、試用開始から14日を過ぎて解雇を行う場合は、通常の解雇と同様の手続きを踏まなければなりません。
具体的には、解雇の際には少なくとも30日前に労働者に対して解雇予告をする必要があり、30日前に予告をしない場合は、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
すなわち、解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の、解雇日の10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことが必要です。
関連記事:
・もしものために、知っておきたい…従業員を解雇するときに必要な手続きとは?
試用開始から14日以内に解雇する場合
試用開始から14日以内に解雇する場合は、労働基準法第21条の規定により、解雇予告をすることなく解雇を行うことが可能です。
しかし、この規定は、試用開始から14日以内の解雇が完全に自由であるとするものではありません。試用開始から14日以内であっても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇を行うことはできないことに留意が必要です。
解雇の際の注意点
労働契約法では解雇について、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要であるとしています。遅刻や欠勤を繰り返す社員であっても、口頭での注意だけでなく、文面での注意や減給措置などの段階的なステップを踏むことで、客観的な証拠を残すことが重要です。
また、能力不足という理由で解雇する場合には、短い試用期間で能力不足の判断ができるのか、プロセスを見ずに成果だけで判断をしていないか、といったポイントに注意しましょう。
試用期間の運用にあたっての注意点
企業による試用期間の設定には一定の合理性が認められ、試用期間中の解雇は通常よりも広い範囲で認められます。しかし、試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれることから、試用期間を設ける場合は適切に運用することが必要です。
試用期間の運用にあたっては、下記の点に注意するようにしましょう。
長期にわたらない期間を設定すること
試用期間の長さを制限する法令等はありませんが、その適性を判断するのに必要な合理的な期間を超えた長期の試用期間を設けた場合は、民法における公序良俗違反として認められない可能性があります。
例えば、試用期間は原則として3ヶ月程度とし、当該従業員の同意を得て6ヶ月まで延長できるとするなど、試用期間は長期にわたらない期間で設定するようにしましょう。
また、試用期間の延長にあたっては客観的な合理性が必要であるとともに、試用期間を繰り返し延長することは認められないという点にも留意が必要です。
適切な労務管理を行うこと
試用期間中の従業員についても、適切な労務管理を行うことが必要です。都道府県労働局長の許可なく法が定める最低賃金を下回ることはできないほか、時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
また、試用期間中であっても、雇用保険や社会保険などの加入要件を満たしている場合はこれらに加入する必要があることから、適切に加入手続きを行わなければなりません。
関連記事:
・

長時間労働削減のための施策の1つに、残業の事前承認制度があります。本人による事前申請に対して上司が承認した場合にのみ残業を行うという仕組みで、残業時間を減少するとともに、メンタルヘルスの改善効果も認められています。今回はそんな残業事前承認制度について、得られる効果、導入する場合の注意点について解説します。
事前承認制度とは
昨今、過剰な長時間残業は多くの社員から忌避される傾向にあります。様々な企業で社員に長時間の残業を強制したり、その分の残業代を支払わなかったり、さらにはこうした事実を隠蔽している実態が露見して、厳しく糾弾されるようになりました。こうしたなか、ホワイトな企業イメージを得ることが重要視されるようになり、ブラックな労働環境にしないために社員の残業を管理し削減する試みも見られます。事前承認制度もそのような戦略の内の1種類に数えられます。社員が元々の労働時間を超えて仕事をする場合、その残業の可否と長さについて上司か担当の許可を得る必要がある、等と規定されます。
メリット
- 無駄な労働時間と給与を削減
残業事前承認制度を採用した場合、サービス残業等の根絶の他にも、不必要な残業を防止することができます。残業をするのに合理的な理由が必要となるので、残業代目当ての残業や、人を待って愛想でこなす残業、やる気が無いために仕事が後ろ倒しになって生じる残業など、非効率的で無駄な残業を減少させられます。また、仕事に期限が設けられるため、より意欲的に取り組むことが期待できます。 - 社員のメンタルヘルス改善
労働が適度な量に制限されていることは、社員のメンタルヘルスへの好影響も見込めます。厚生労働省により公表された平成29年版過労死等防止対策白書では、労働時間の正確な把握が残業時間を減少させると分析されています。より具体的には、労働時間を正確に把握しかつその分の給与を全額支給することや、残業を行う場合に上司や担当が残業を承認することは、残業時間の減少とメンタルヘルスの良好化などに繋がること、残業時間を0時間に近づけることは、メンタルヘルスの良好化などに繋がること等が記載されています。残業承認制度はこれらの実現を可能にする制度であり、社員のメンタルヘルスの改善推進に繋がると言えます。
注意点
残業事前承認制度を導入する際に気を払わなければならない点として、黙示的指示という概念があります。もし残業の命令や承認を明示的に行っていなくても、現実的に考えて労働時間内で終わらない量の仕事が要請されていた場合、社員が行った時間外労働は残業時間とみなされます。例えば、仕事の納期等が元々の労働時間内では守れないケース、企業側が残業の存在を知りつつ放置もしくは黙認していたケースなどが該当します。
関連記事:
・あなたの会社は大丈夫?―不合理な残業削減による「時短ハラスメント」
・残業が制限される!? 政府の働き方改革実現会議、「36協定」の運用見直しへ
無断で残業した社員にその分の給与の支払いは義務?
企業によっては、無断での残業には給与を支払わないと予め規定していることがあります。とは言っても、仕事をするつもりは無かったのに突然プロジェクトでの不具合が生じて時間外労働をしてしまった、といったことも起こり得ます。この様な場合、残業代は支払われるべきでしょうか?実は支払う義務が生じることもあるのです。労働時間とは企業等の指揮命令下にある時間のことを指し、企業のためにやむを得ず時間外労働をしている場合は残業が生じたと見なされるためです。
無断での時間外労働が残業と見なされなかったケース
社員が元々の労働時間を超えて仕事をした分の給与支払いを認めるか認めないか、という問題については今まで様々な判例が存在します。残業代支払いが命じられる場合には黙示的指示が働いていたと判断されるケースが多く、その際、企業側が予め申請の無い時間外労働には給与を支払わないと規定していたとしても、支払いの義務は免れません。では逆に、どの様な時間外労働であれば残業と見なされないのでしょうか。裁判において企業側の言い分が部分的もしくは全面的に認められた、つまり労働時間外の仕事であったが支払いが必要とは認められなかったケースを幾つか紹介します。
- 吉田興業事件(平成2年)
こちらは、ビルの管理業等を行う企業で働く社員が、業務委託されていた水資源開発公団の出張所に住み込みで管理や清掃等の仕事を行っていたことについて、時間外労働や休日を返上しての労働であると主張し、給与の割り増しを請求したケースです。これについて裁判所の判断は、公団職員の終業後の戸締まり等の仕事を行うために公団職員が退出するまで待機している時間は手待ち時間として労働時間に含めて考えるべきであるとしながら、このケースでは公団職員の退出後に行う業務に要する時間は非常に短く、かつ、いつその業務を行うかはその社員の自由であることから、社員が通常の労働時間の前後に行った戸締りなどの業務は企業や公団の指示によるものではなく、その社員の自発的な行為というべきであると判断し、残業代の支払いは不要と結論しました。 - ニッコクトラスト事件(平成18年)
こちらは、日本銀行の寮の管理や調理等の仕事を住み込みで行っていた社員が、労働日においては元々の労働時間を超えて働き、労働日以外にも長時間にわたり仕事をしたとしてその分の割増給与を請求したケースです。これについて裁判所では、日本銀行がその社員に委託した仕事の業務量は労働時間内で充分に処理できるものであったと断じ、その社員は自発的な判断によって企業側から委託された仕事や指示の範囲を超えて働いたものと結論したため、企業側の残業代支払いの義務は認められませんでした。
導入に際して
残業が建前の上ではないものとされていても事実上は存在すると認められれば、黙示的指示が働いているとして企業側が支払いの義務を負うことになります。制度が形骸化し、申請されない残業が横行することは避けなければなりません。したがって、社員が残業しないように上司や担当が注意を怠らず、どうしても残業が必要な際には毎回の申請を徹底させると共に、日頃から社員に振り割る業務を適度な量に留めることが重要と言えます。
関連記事:
・【2024年5月更新】残業代はすべて割り増しに?労働基準法で定める割増賃金とはどんなもの?
・年俸制でも残業代の支払いが必要?!年俸制の性質や注意点について解説!
まとめ
残業事前承認制度は、不必要な残業の削減のみならず、社員の仕事の効率化やメンタルヘルス改善にもつながると考えられています。導入すればそれなりの手間や管理が求められますが、非効率な残業とその分の給与の支払いを黙認するよりは生産的ですから、必要以上の残業が横行している現状の改善を望む企業は、1つの手段として検討してみてはいかがでしょうか。
改善の機会を与えること
試用期間中は、定期的に従業員の業務について評価の機会を設け、十分な指導や教育を行うことが重要です。従業員が適性に欠けると判断される場合でも、適切な指導を行い改善の機会を与えるなど、できる限り解雇を回避する努力をするようにしましょう。
まとめ
試用期間は、従業員の適性を判断するための「お試し期間」という性質を持っていますが、その法的性質や従業員へ与える影響などを考慮すると、何の理由もなく自由に解雇できるというものではありません。
試用期間を設ける場合には適切に運用するとともに、試用期間中の解雇を行う場合は適正な手続きを踏んで行うようにしましょう。
監修者

社会保険労務士として独⽴開業時より、ソニーグループの勤怠管理サービスの開発、拡販等に参画。これまでに1,000社以上の勤怠管理についてシステム導入およびご相談に対応。現在は、社会保険労務士事務所の運営並びに勤怠管理システムAKASHIの開発支援を実施。