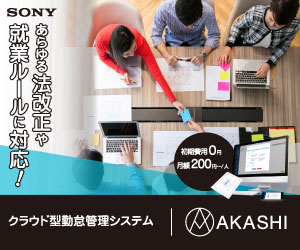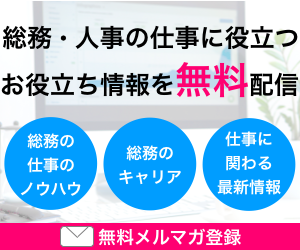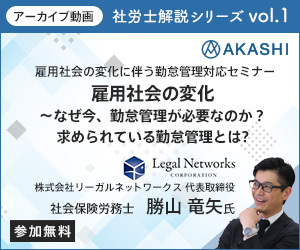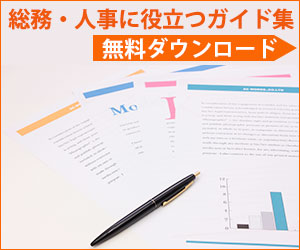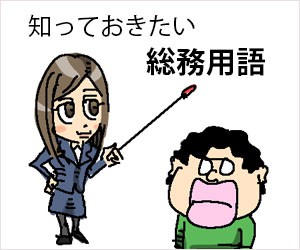データドリブンとは、意思決定を経験や直感ではなく、客観的なデータに基づいて行う手法を指します。膨大な情報を活用し、業務の効率化や顧客満足度の向上を図れることから注目されています。導入により属人的判断を防ぎ、再現性ある成果が期待できますが、データ分析の体制構築や人材育成が課題となることもあります。今回は、データドリブンが注目される背景やそのメリット・デメリットについて解説します。
目次
データドリブンとは
意思決定における手法の一つ
データドリブンとは、「数値」や「情報」を意味する「データ(data)」に「駆動される」や「推進される」を意味する「ドリブン(driven)」を組み合わせたビジネス用語で、経験や直感ではなく客観的な数値や情報に基づき行う意思決定の手法の一つです。特に近年では、従来の勘や経験ではなく、データに基づく経営を意味する「データドリブン経営」「データドリブンマネジメント」などが大きな注目を集めています。
データドリブンが注目される背景
以前からデータの利活用は進められてきましたが、近年特にデータドリブンが注目を集める背景には、変化の激しいビジネス環境、顧客行動の多様化、デジタル技術の発展などがあります。「VUCA時代」といわれて久しい現代では、データを活用して市場の変化に素早く対応しなければなりません。また、顧客の価値観や消費行動が多様化しているのも、データドリブンが注目を集める要因です。情報が溢れる現代社会では、データを利活用して顧客の行動を分析し、予測する必要があります。さらに、デジタル技術の発展もデータドリブンには欠かせないトピックです。AIなどの登場によってデータの分析が飛躍的に容易になり、重要な経営判断にデータを活用する企業も増えてきました。
関連記事:
・有能な人材の獲得へ、ジョブカード制度を活用しましょう!
・ジョブローテーション制度とは? メリットとデメリットを解説
・人事権とは?人事権の濫用を防止するためのポイント
データドリブンのメリット・デメリット
メリット1:根拠のある意思決定ができる
従来の勘や経験に基づく意思決定には、再現性が低いという欠点がありました。例えば、ある施策を実行し成功したとしても、その原因が明確ではないためノウハウの蓄積も難しく、異なるタイミングで異なる人材が実行しても必ずしも成功するとは限りません。一方、データドリブンは根拠が明確で一貫性もあるため、再現性の高い意思決定を下すことが可能です。結果と原因の因果関係も明確なので、成功までの道筋や改善のための施策なども計画しやすくなります。
メリット2:分析による潜在的な課題・強みが得られる
勘や経験に基づく意思決定は原因が明確ではないため、結果を分析するのが困難という欠点もあります。例えば、ある施策が失敗に終わったとしても、結果と原因の因果関係が不明瞭で、施策が抱えていた課題や問題を分析するのは難しいかもしれません。一方、データドリブンは根拠が明確なので、結果を分析して潜在的な課題や自社の強みを可視化することが可能です。データの収集や蓄積も容易に行えるため、改善施策の立案なども高い精度で実行できます。
メリット3:他社との差別化を図る施策の創出
蓄積したデータによって、他社と差別化を図る独創的な施策を創出できる可能性があるのも、データドリブンのメリットです。情報が溢れる昨今、従来の勘や経験だけに頼った意思決定では、差別化は難しいかもしれません。例え独創的なアイディアを思いついたとしても再現性が低いため、高度情報化社会のなかではすぐに陳腐化してしまう可能性があります。結果と原因の因果関係を分析しやすいデータドリブンではあらゆるデータを可視化できるため、いままで気付かなかったような新たな切り口で独創的な施策を創出できるかもしれません。
デメリット:データ分析の専門家が必要
データドリブンの唯一にして最大のデメリットは、データの分析や活用に精通した専門性の高い人材が必要だということです。データドリブンではデータの収集や分析が重要となるため、最適なデータを適切に活用するスキルが求められます。例えば蓄積したデータに不備やバイアスがあると、誤った意思決定を下してしまう恐れもあるでしょう。特にデータドリブン経営を標榜している場合、データの不備や間違った解釈は経営を揺るがしかねない大きな問題です。データドリブンにはデータエンジニアやデータアナリストが必要不可欠ですが、社内で必要な人材を確保するのは難しいかもしれません。
データドリブンの進め方
該当データの収集
データドリブンを進めるには、まずは目的達成に必要なデータを収集し、蓄積することが求められます。データの収集や蓄積は、Web解析やデータマネジメントプラットフォームなどを活用するのが一般的です。アンケートやインタビューなどアナログな手法でデータを収集する場合は、AI-OCRやAI文字起こしツールを活用すると効率的にデータを蓄積できます。
集めたデータの可視化・分析
蓄積したデータはそのままでは視認性が悪く情報を読み解けないため、必要に応じて表やグラフなどの形に可視化します。データを可視化すればデータ間の関係性も分かりやすくなるため、傾向や法則などを把握して分析を進めることが可能です。表計算ソフトやビジネスインテリジェンスツールなどを活用すると、効率的にデータを可視化できます。
分析の結果から意思決定を行う
データを可視化できたら分析を進め、得られた情報に基づき意思決定を行います。データから得られたサジェスチョンをより深く分析したい場合は、データエンジニアやデータアナリストの力を借りるのも一つの方法です。専門家の協力によりデータを分析できたら、データが示す情報に従い意思決定を行い、具体的な施策まで落とし込んでいきます。
施策の実行・改善
具体的な施策まで落とし込めたら施策の実行と改善を繰り返し、PDCAサイクルを回します。データドリブンは、一度施策を立案・実行して終わりではありません。データの収集・分析、施策の立案・実行、結果の分析、改善施策の立案・実行を継続的に実施し、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。PDCAサイクルを回し続けることでデータドリブンが社内に根付き、継続的な成長と競争力の向上につながります。
まとめ
今回はデータドリブンについて解説しました。データドリブンとは、データに基づき行う意思決定の手法の一つです。勘や経験に基づく従来の意思決定は再現性が低いため、変化の激しい市場において競争力を維持するのは難しいかもしれません。根拠が明確なデータドリブンを駆使し、他社との差別化を図ることが重要です。