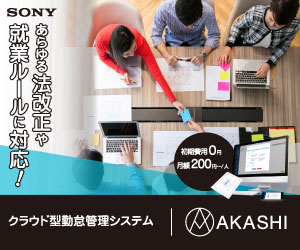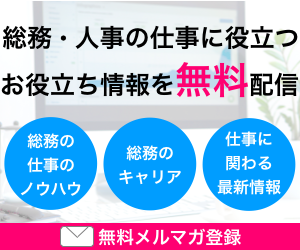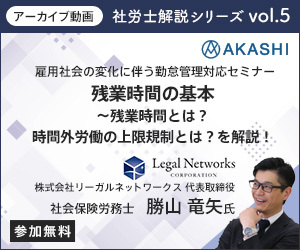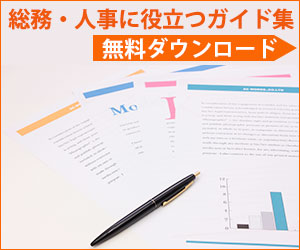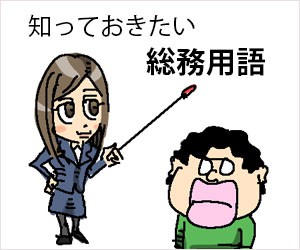コアコンピタンスとは、企業が持つ「他社には模倣できない中核的な強み」を指します。顧客に独自の価値を提供し、複数市場で競争優位を築く基盤となります。ケイパビリティが業務遂行のための組織的能力であるのに対し、コアコンピタンスはそれらを統合した持続的な強みです。見極めには、強みの模倣困難性や応用可能性を評価することが重要です。今回は、コアコンピタンスの概要やケイパビリティとの違い、見極め方などについて解説します。
目次
コアコンピタンスとは?
企業が持つ他社には模倣できない中核的な強み
コアコンピタンス(core competence)とは、日本語で「中心」や「中核」を意味する「core」 に、「能力」や「資産」を意味する「competence」を組み合わせたビジネス用語です。ビジネスの分野では、競合他社には模倣が難しい、企業の中核となる能力や資産を意味します。コアコンピタンスという考え方は、C.K.プラハラード氏とゲイリー・ハメル氏の2名が1990年に寄稿した論文で提唱した概念です。論文の中で両氏は、コアコンピタンスは競合優位性を維持して新たなビジネスチャンスを掴むための必要不可欠なものと述べています。
コアコンピタンスが重要視される背景
コアコンピタンスが重要視される背景には、変化の激しい市場環境と顧客ニーズの多様化があります。ビジネスがグローバル化する昨今、従来のように過去の実績や現在の業績に着目した旧態依然とした経営戦略では、市場競争に勝ち残ることは難しいでしょう。目まぐるしく変化し予測困難な「VUCA時代」を生き抜くには、革新的な技術開発や生産プロセスの改善が必要不可欠です。また、多様化する顧客ニーズに応えるため、企業は自社の中核となる強みを認識し、付加価値の高い製品やサービスを提供する必要があります。変化への対応や付加価値の提供において、最も重要な概念がコアコンピタンスという考え方です。
ケイパビリティとの違い
コアコンピタンスと類似した概念に、ケイパビリティという考え方があります。ケイパビリティ(capability)とは、企業が持つ組織全体の強みや能力です。前述の通り、コアコンピタンスは競合他社が模倣できない企業の中核となる強みや資産を指します。コアコンピタンスが特定の中核技術を指す一方、ケイパビリティは組織全体の強みを指す概念です。特定の技術に注目するコアコンピタンスに対し、開発や販売のプロセスにも着目するのがケイパビリティの特徴でもあります。
関連記事:
・カルチャーデックとは?作成方法や企業が活用するメリットについて徹底解説
・採用ブランディングとは?メリットと進め方について解説
・OODAループとは?OODAループの具体的な4ステップとともに解説
コアコンピタンスの3つの要件
顧客に付加価値を提供できる
企業の中核でもあるコアコンピタンスである以上、顧客に対して付加価値を提供できなければなりません。多様化する顧客のニーズに応えられなければ、企業として利益を生み出すことが難しいからです。逆に言うと、付加価値を生み出さない技術は、コアコンピタンスとは言えません。C.K.プラハラード氏とゲイリー・ハメル氏の両氏は論文の中で、コアコンピタンスを見極める視点として、「模倣可能性」「移動可能性」「代替可能性」「希少性」「耐久性」の5つを挙げています。代替が難しく希少性の高い技術こそが、その企業にとって付加価値を生み出すコアコンピタンスです。
競合他社による模倣が困難である
コアコンピタンスである重要な要素に、競合他社による模倣は困難であることが挙げられます。見極めの視点にも模倣可能性が含まれており、コアコンピタンスを構成する重要な要素の一つです。逆に、競合他社に容易く模倣されるような技術は、コアコンピタンスとは言えません。コアコンピタンスである以上は模倣が難しく、希少な技術である必要があります。なぜなら、模倣が簡単な技術はすぐに他社の追随を許すため、いずれ市場競争に敗れてしまう恐れがあるからです。市場競争に勝ち抜くには、模倣の難しい独自性の高い技術でなければなりません。
多岐にわたる製品や市場に応用できる
見極めの視点には、移動可能性が含まれています。移動可能性とは、特定の技術がさまざまな製品や市場に応用できるという考え方です。前述の通り、ビジネスがグローバル化した現在、市場環境の変化は激しく、顧客のニーズも多様化しています。変化が激しく予測困難な「VUCA時代」を生き抜くには、応用が効く独自性の高い技術を確立しなければなりません。中核となるコアコンピタンスは、幅広く応用できる移動可能性の高い技術である必要があります。また、移動可能性や模倣可能性、代替可能性、希少性を長期的に保ち続ける耐久性も、コアコンピタンスを形成する重要な要素の一つです。
コアコンピタンスの見極め方
自社の持つ強みを把握する
コアコンピタンスを見極め決定するには、まずは自社の強みを把握することが第一歩です。ケイパビリティにも注目し、自社が持つ強みや能力を多角的に洗い出すことから始めます。例えば、技術・能力・特性・人材・製品・サービス・組織風土・企業文化・ノウハウなどは、コアコンピタンスになり得る重要な資産です。コアコンピタンスとまでは言えないような資産であっても、特定の市場においては競合優位性を持っている可能性があります。このステップでは、思いつく限りの強みや能力を洗い出すことが重要です。
自社の持つ強みがコアコンピタンスになるか評価する
強みや能力の洗い出しが完了したら、コアコンピタンスになり得る資産かどうか、評価を行います。強みや能力を評価する際には、模倣可能性・移動可能性・代替可能性・希少性・耐久性の5つの視点に着目することが非常に重要です。これらを満たさない強みや能力は、コアコンピタンスになり得ません。また、前章で解説したコアコンピタンスの3つの要件も重要な視点です。なお、強みや能力の評価は、一度で終わらせてはいけません。市場環境の変化や競合他社との関係を考慮し、繰り返し評価を実施することが重要です。
自社の強みを絞り込みコアコンピタンスを決定する
繰り返し実施した評価を基に、コアコンピタンスになり得る自社の強みや能力を絞り込みましょう。コアコンピタンスは今後の戦略や方針に大きな影響を及ぼすため、このステップは非常に重要です。一度決めたコアコンピタンスは原則、簡単に変更することはできません。そのため、経営層やマネジメント層で繰り返し議論を重ねることが重要です。コアコンピテンスを決める際は、「市場への参入が可能か」「他社による模倣のリスクはないか」「将来さらなる進化や改善が期待できるか」などに注目して決定してください。
まとめ
今回はコアコンピタンスについて解説しました。コアコンピタンスとは、競合他社が模倣できない自社の中核となる強みです。予測困難な「VUCA時代」とも言われる変化の激しい昨今、付加価値を生み出すコアコンピタンスは非常に重要です。今回解説した5つの視点や3つの要件を意識し、誰にも真似できないコアコンピタンスを決定しましょう。