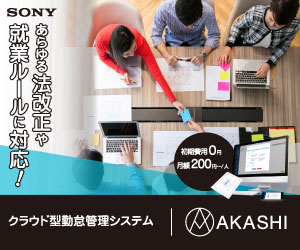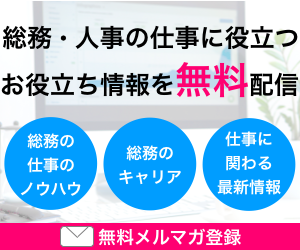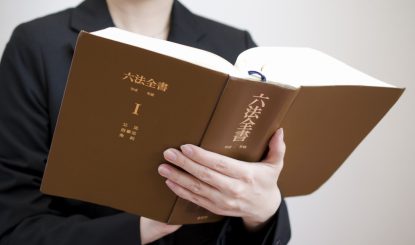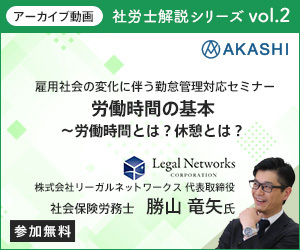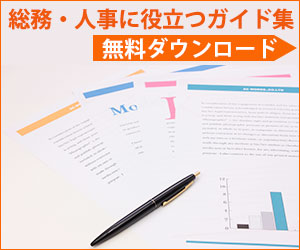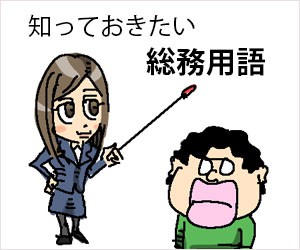諭旨解雇とは、重大な規律違反があった従業員に対し、懲戒解雇を回避し自発的な退職を促す処分のことを指します。懲戒解雇よりも退職金支給などの面で処遇が緩やかで、退職理由も比較的穏便に済ませられます。ただし、手続きには十分な事実確認と本人への弁明の機会が必要です。今回は、諭旨解雇の概要や懲戒解雇との違い、適切な手続きなどについて解説します。
目次
諭旨解雇とは
懲戒処分の手続きの一種
諭旨解雇は「懲戒処分」に含まれる手続きであり、該当する従業員に退職届の提出をうながし、提出後に解雇させる処分を下します。「諭旨」とは、「理由を諭し、告げる」という意味合いがあり、懲戒処分になりうる事例を発生させた従業員に対して退職を告げたのち、企業側と従業員の双方が納得したうえで退職届を提出し、退職の手続きを進めることが大きな特徴といえるでしょう。
懲戒解雇との違い
諭旨解雇は、懲戒処分のなかで上から2番目に重いとされる処分です。では1番目は何かというと、それが「懲戒解雇」です。懲戒解雇は、該当する従業員の同意なしに解雇を実施する処分であり、従業員への説得や理由説明・同意を得る機会を与えることなく退職の手続きを進めます。また、企業の規則によっては退職金が全額もしくは一部支払われないケースも考えられます。
退職勧奨との違い
退職勧奨は、企業が従業員に対して退職を勧める行為を指します。ここまでは諭旨解雇との違いはありませんが、退職勧奨はあくまで促す効力のみで、解雇を予告することはできません。そのため、退職勧奨を実施して仮に従業員がそれを拒否したとしても、ペナルティが発生することはありません。一方で諭旨解雇は従業員が退職処分に応じなかった場合、懲戒解雇に踏み切ることもできるようになるため、強制力という点で大きな違いがあります。
関連記事:
・一時帰休とは?一時帰休を行う目的と注意点について解説
・人事権とは?人事権の濫用を防止するためのポイント
・【社労士監修】試用期間中に解雇はできる?注意点などを徹底解説
諭旨解雇を実施する注意点
就業規則で諭旨解雇処分が定められているか確認する
まず、企業が就業規則で「懲戒処分」の方法として、諭旨解雇処分が定められていることが条件です。就業規則に定められていないにもかかわらず諭旨解雇を強行してしまうと、不当解雇として訴えられる可能性も十分に考えられます。また、諭旨解雇を行使するに値するかどうかの判断をするためには、懲戒事由も就業規則に詳しく定める必要があります。
従業員に納得できる理由・方針の説明が必要
就業規則に定められる内容にのっとり、諭旨解雇の手続きを行使するに値するほどの事由であったことを、従業員から納得を得られるまで詳しく理由説明をする必要があります。従業員の解雇を促すほど重大な処分であるがゆえに、客観的に解雇することが妥当であることが説明できない場合、従業員に退職を納得させることは難しくなるでしょう。
解雇が無効になる可能性がある
また、解雇事由に妥当性がないと判断される場合、諭旨解雇の処分が法的に無効となる可能性があります。労働契約法という法律において、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」という記載があります。また、解雇においても同様に、権利濫用として無効とする記載がなされています。
諭旨解雇の手続き方法
諭旨解雇に該当する内容の調査
まず始めに、該当の従業員が本当に諭旨解雇の処分に値する事実があったのか、もしくはそのような行為を行ったのかを調査する必要があります。事実確認を怠ると、前述のとおり諭旨解雇の処分が無効になるばかりか、従業員側から訴えられてしまう可能性も考えられます。該当の従業員の内容調査と事実確認を行い、調査の結果諭旨解雇が妥当であると判断しているプロセスを踏むことで、処分の妥当性を確立させることができます。
従業員に弁明の機会を与える
懲戒解雇とは異なり、諭旨解雇は従業員側からの弁明を経て退職届の提出を促す機会を与えます。弁明の機会を与えた証拠がない場合も、諭旨解雇処分を無効とされる可能性があるため、必ず本人の意見を聴く機会を設けましょう。このとき、「弁明の機会を与えた」という証拠を残すために、事情聴取書などとして書類にまとめて、記録をしておくと良いでしょう。また、処分を検討している従業員以外からの情報をヒアリングした場合も、記録して残しておくとトラブルが発生した際の証拠として扱えるようになります。
弁明を踏まえて処分を決定する
従業員の弁明を確認したのち、その内容を踏まえて実際の処分を決定します。懲戒解雇とは異なり、このときの弁明の内容によっては、十分に反省が認められるなどの理由によってそのまま退職を迫るのではなく、処分が軽くなるケースもあります。改めて諭旨解雇の処分が適当なのかを再度精査し、それでもなお処分が妥当であると判断された場合は、従業員へ解雇の処分を伝えます。
従業員に処分を通知する
従業員に諭旨解雇処分になったことを書面で伝えるため、処分通知書を作成し、該当の従業員に交付します。従業員がこの処分を受け入れることで退職届を提出し、解雇というプロセスになります。このとき、前述のとおり退職手続きの提出を従業員が拒否した場合は懲戒解雇へ切り替えることになるため、事態を長引かせないためにも、処分通知書には退職届の提出期限を記載しておくと良いでしょう。
まとめ
諭旨解雇は、懲戒解雇に次ぐ重い処分にあたります。実際にこの処分を実施する際には、該当の従業員が違法性のある行為などを実際に行ったのか、入念に事実確認を行うことが重要です。理由に妥当性がない場合など、無効と判断されるケースも考えられるため、就業規則にはあらかじめ懲戒処分の事由を定めておきましょう。