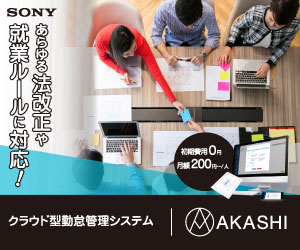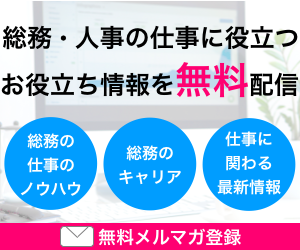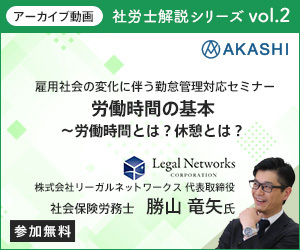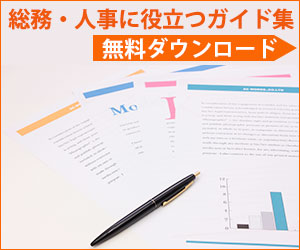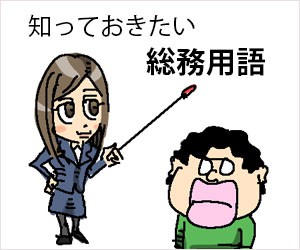RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)とは、採用活動の際に業務内容や職場環境の「良い面だけでなく、悪い面も含めて」正確に伝える手法のことを指します。入社後のギャップを防ぎ、早期離職の抑制や定着率向上が期待できます。一方で、伝え方によっては応募者の不安を招く可能性もあるため、バランスの取れた情報開示が重要です。今回は、RJPのメリット・デメリットと、導入時のポイントなどについて解説します。
目次
RJPの理論とは
自社の「ありのまま」を伝える採用手法
RJPとは「Realistic Job Preview」の略で、「仕事について、ありのままの情報を応募者へ伝える手法」のことを指し、アメリカの産業心理学者ジョン・ワナウスによって提唱されました。企業の「良い面」「(他企業と比較して)優れている面」をアピールポイントとして応募者に伝えるだけでなく、「悪い面」「劣っている面」についてもある程度開示することで、入社後の定着率の向上などさまざまな効果に寄与するとされています。
RJPの考え方が注目される背景
RJPの考え方が注目される背景には、早期離職の増加傾向があります。近年「退職代行サービス」の利用者が散見されることは、これを如実に表す一例といえるかもしれません。加えて、企業へ透明性・公平性といった要素を求める、若者の価値観の変化に迎合する採用手法の必要性が高まったともいえます。
早期離職の多くのケースでは、入社前後のギャップが大きいことが離職理由の一因となっていますが、RJPによりマイナス面を包み隠さず伝えることで、ギャップを軽減する効果が見込めるでしょう。
また、従来の「とにかく多くの応募者を集め、選考の過程でふるい落とす」といった母集団形成は、採用の間口を広げられる反面、採用工数の増加を招くのがデメリットです。
RJPでは悪い面を開示することで、開示しない場合と比べて初期の段階で応募者が辞退する可能性があるため、より効率的な母集団形成・採用フローの最適化に貢献できる可能性があります。
RJPを構成する4つの要素
RJPは、以下4要素の組み合わせによって効果を発揮するとされています。
- セルフ・スクリーニング効果
企業だけでなく応募者からも企業を評価する、「双方向的な選択」を促進する効果です。本格的な選考フローに進出する前に情報開示を行い、応募者自身が企業とのマッチング度を再考する機会を設けることで、ミスマッチの防止が期待できます。
- ワクチン効果
良い面だけを知ることによる「過剰な期待を生まない」ための効果です。入社前後のギャップを抑止し、モチベーション低下を防げる可能性があります。 - コミットメント効果
企業が「悪い面をも開示している」という姿勢そのものを、透明性・公平性におけるアピールポイントとして伝える効果です。企業の誠実さを強調し、貢献したいという気持ちや帰属意識を高める効果があります。 - 役割明確化効果
「入社後の業務イメージの具体化」に貢献する効果です。「入社後に果たしてほしい役割」を応募者に明確に伝えることでギャップを軽減するとともに、「期待に応えたい」という意識を醸成するエンゲージメント向上効果も見込めます。
関連記事:
・採用ブランディングとは?メリットと進め方について解説
・アルムナイ採用とは?導入することで得られるメリット・デメリットについて
・職業能力評価基準を導入し、自社に合った人材を採用しましょう
RJPのメリット・デメリット
メリット1:採用マッチング率・長期定着率の向上
悪い点を開示してなお応募に至った場合、悪い点を加味してあまりある魅力をその企業に感じている、より熱意ある応募者を採用できる可能性が高まるでしょう。結果として、採用後の定着率向上や、人材としての業務マッチング率向上が見込めます。
メリット2:採用・選考プロセスの明確化
一般的な選考において、初期段階での母集団の人数はそのまま採用プロセスにおける工数の多寡に直結するため、RJPで人数を減らすことはコスト面でのメリットともなります。
また、ネガティブな面を先立って伝えた場合、その後のフローにおいては「ネガティブ面もある程度織り込み済みの応募者」として扱うことができます。そのため、面接での質問事項をより現実の業務内容に即したクリティカルな点に絞り込むなど、時間的コストについても削減につながる可能性があるでしょう。
デメリット:マイナス面による求人応募減の可能性
上記のメリット2と表裏一体ではありますが、ポジティブな面だけを伝えた場合と比べれば、当然ながら母集団は減少する可能性が高くなります。そのため、とにかく母集団を確保したい、事業規模拡大により人数を揃えたい、といった時期の企業には、RJPは不向きな採用手法といえるかもしれません。
RJPを導入する際のポイント
現場の情報収集を徹底する
RJPで開示する情報に関しては、ポジティブ・ネガティブの両面について、情報の正確性に万全を期す必要があります。採用担当と現場の担当者で認識に齟齬がある場合、逆に入社前後のギャップを深めるおそれもあり、企業への信用や帰属意識すら損なう可能性があるためです。
採用担当側で知り得た業務内容・人間関係などについては、事実に即しているかの確認を現場との間で徹底しましょう。その際は、応募者の感じるギャップを可能な限り小さくするため、現場の変化に応じて最新の情報へ更新することも重要です。
ポジティブ・ネガティブ情報のバランスを考慮する
ネガティブな情報を開示する場合、割合としては2~3割程度に留め、必ずその理由や対応するポジティブ情報を提示することが求められます。単に「ここがダメ」ではなく、ネガティブな面を応募者が必然性を持って受け入れられることが重要となるためです。
例えば「営業職は残業が多い」というネガティブ要素がある場合、「営業職の多くが残業時間を顧客情報の整理や提案書作成に充てており、売上高にもつながっているが、働き方次第で削減可能」「サービス残業ではなく、きちんと給与としても反映されている」といったポジティブ要素、発生原因を伝える必要があるでしょう。
情報の伝え方を工夫する
配布資料等の文章や口頭で伝えるだけでなく、社員インタビューや映像コンテンツなど伝え方を工夫することで、ネガティブ面を明らかにしつつも、受け入れやすくなる効果が期待できます。過度に企業に好意的な構成は逆に応募者の疑念を生むおそれもあるため、インタビュー内容が恣意的でないかは必ずチェックしておきましょう。
また、最も入社後の現場に近い体験として、トライアルやインターンシップで雰囲気を掴んでもらうのも効果的です。その場合でも、上述した「ネガティブ要素のフォローや理由の開示」は、質疑応答や補足説明などの形で行っておいた方が無難でしょう。
まとめ
RJPは、企業と応募者が相互に選択の機会を設けるために有用な採用手法です。採用コスト削減効果はもちろんですが、「量より質」を重視する手法ともいえ、応募者に対して「清濁併せ呑む」要請をもつ、多くの企業に適した考え方といえるでしょう。実施の際は情報の正確性を検証するとともに、ネガティブな情報に偏り過ぎないようなバランス感覚と、応募者が現場や現役社員の雰囲気を掴みやすいような媒体の工夫が必要です。